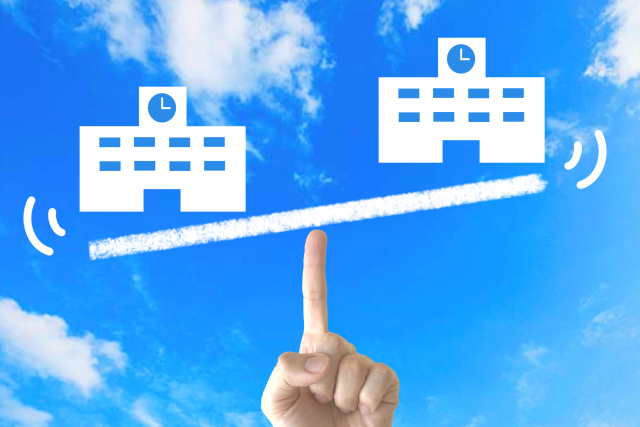春、新生活の季節です。
3人兄弟の我が家の三男はこの春から大学生になりました。
ようやくゆっくりと今までのことを振り返る余裕ができたので、三男の大学受験についてまとめてみたいと思います。
タイトルは「私立併願なし!?で挑んだ我が家の大学受験体験記」としましたが、その名の通り私立大学の併願を結果的に押さえることなく挑んだ受験でした。
今回は共通テスト後の自己採点から受験校決定までを振り返ります。
自己採点の結果は…?
無事2日間のテストを終了し、迎えた月曜日。
3年生は全員が学校に登校して共通テストの自己採点を行います。
そしてその日は学校が終わった後、必ず塾に行ってその採点結果を報告することになっていました。
塾への報告の後は二次対策の学習もして、家に帰ってきたのは21時過ぎ。
本人から出た採点結果は想定外の「780点くらい取れてた」でした。
三男はここまで何度も模試を受けてきていましたが、平均して得点率は7割まで届かないことがほとんど。
まさか、まさかの得点率です。

周囲もびっくりしましたが、一番びっくりしていたのは本人。
確かに手ごたえはあったとのことでしたが、まさか本番で一番出来がいいとは思ってもみませんでした。
志望校を決めるプランは3つ
さて、共通テストを受ける前に学校から言われていたことがありました。
志望校を決めるときにはプランを3つ立てること。
プランAは共通テストが想定より良かった場合。
プランBは共通テストが想定通りだった場合。
プランCは共通テストが想定より悪かった場合、という具合です。
三男のプランは以下の通り。(大学名は伏せます)
プランB:前期はC大学(県外ですがB大学より少し偏差値が上)、後期はB大学
プランC:前期はB大学、後期もB大学
普通ならプランCの後期はB大学より偏差値が下の大学を選びたいところですが、近隣の国公立大学に三男が学びたい分野を設定している学校がなかったため、かなり最悪のプランになる予定でした。
そして今までの模試結果からすると、よくてプランB、最悪はプランCでの受験を覚悟していたのです。
最後の決定は塾の先生と話し合い
予想以上に共通テストの出来がよかった三男ですが、最後は塾の先生と話し合って受験校を決めることにしました。
塾での合格判定は、A大学がB判定、C大学はA判定、B大学は後期日程でもA判定が出ていました。
一般的にB大学の後期日程では旧帝大や難関国公立クラスでないと合格が難しいと言われていたのですが、共通テストの得点率に加えて後期日程の試験が面接だけ(しかも配点は0)ということで、ほぼ大丈夫だろうとのこと。
ただ、A大学の三男が志望する学科は募集人数が少なく、例年、志願倍率は5倍を超えていました。
私はこの倍率の高さがとても心配だったのですが、これを踏まえても塾の先生はA大学で受験してもいいだろう、との判断。
さらに本人がC大学についてあまり乗り気ではなく、受験するならA大学で、だめなら地元のB大学でいいとのことでした。
ということで、三男の受験校は「プランA」で決定することになったのです。
次回は二次試験までの間に実は私立大学を受験した件についてまとめます。