子育てをしていると、一度は「学級崩壊」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
私は3人の子供を育ててきた中で、次男、三男の2回に渡ってこの学級崩壊を経験しています。
学級崩壊とはどんな状態なのか、そして保護者としてどんなことができるのかを私の体験からまとめてみたいと思います。
学級崩壊とは
学級崩壊とは、学級が集団教育の機能を果たせない状況が継続し、通常の手法では問題解決が測れない状態に陥ったことを言います(Wikipediaより)
私の子供たちが経験した中では、授業中の離席、私語などで授業の妨害をする、先生の言うことを聞かずに勝手なことをする、などの状態がそれに該当すると思います。
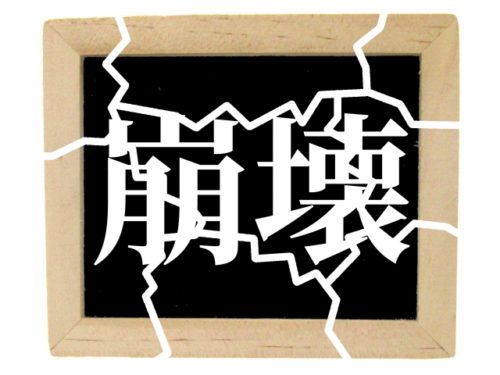
近年では小学校低学年での学級崩壊が多くみられると言われていて、実際に次男のクラスが学級崩壊の状態になったのは小学校2年生のときでした。
また、小学校3年生ころは「ギャングエイジ」といわれ、子供たちが集団というコントロールから自立する時期にあたり、三男のクラスが学級崩壊したのがちょうどこの時期でした。
小学校低学年での学級崩壊
次男のクラスが学級崩壊した小学校2年生の頃、クラスでは個性のある子供が数人いました。
じっとしていられない子供、授業中におしゃべりしてしまう子供がクラスの中にいると、子供たちは当然そっちに引きずられてしまいます。
先生はその子供たちに特性がある、ということを理解しているので、表立った注意をせずにいました。
注意してもどうしてもその個性が出てしまう、と考えていたのだと思います。
しかし、子供たちにはそれが理解できません。
あの子はしゃべっても注意されない。ならば自分もしゃべってもいいはずだ、と考えるのです。
これがひどくなり、最終的には授業中に離席する子供、勝手に私語を続ける子供たちが続出しました。
彼らの一番ひどかった時期には、授業参観で親が見ていても同じように離席したり騒いだりしていました。

学校からはこのような学級崩壊の情報発信は一つもなく、私達はその授業参観で初めてその惨状をみることになりました。
この頃、担任の先生が病気とのことで休職、臨時の先生たちが何人か入れ替わり立ち替わりする状態でした。
こういったことも子供たちには影響を与えたのだと思います。
ギャングエイジの学級崩壊
一方、三男のクラスではちょうどギャングエイジと言われる小学校3年生の頃に学級崩壊に限りなく近い状態になりました。
このクラスにも目立った特性のある子がいて、その子供に振り回されている感じはありました。
それでも何とか頑張っていた子供たちですが、女の子の中では友達関係が複雑になり、男の子は乱暴になるとかなり体力がついているのでおおごとになる年頃。
やはり行き着く先には離席、私語、友達関係の悪化という学級崩壊が待っていました。
学級崩壊を目の当たりにした保護者は
次男のクラスが学級崩壊状態になったとき、保護者は何も知らされていませんでした。
たまたま授業参観で、彼らが普段どおりの姿を見せたことで、私達はびっくりして声も出なかったのです。
担任の先生はコロコロと入れ替わり、何を誰に相談したらよいかわからない状態。
そこでできることは、「とにかく自分の子供だけでもなんとかしよう」という小さな働きを、みんなでやろう、ということでした。
授業参観のあと、子供と向き合い、なぜ離席するのか、なぜ私語をするのかを聞きました。
次男は、「〇〇くんが離席しても、先生は全然怒らない。□□くんが私語をしても先生は怒らない。だからオレだって離席しても私語をしてもいいと思う」と言いました。
小学2年生の考えることです。当然とも言えますよね。
だけどそれでは授業ができない。集団生活は成り立たない。
そのことを根気よく説得しました。
〇〇くんや、□□くんは座っていられない、黙っていられない個性がある。
それを許すべきだ、とはいわないけれど、彼らがやっているから自分がやってもいい、というのは違う。
そのことを一生懸命、話をしたことを思い出します。
休み時間は好きなことをしてもいい。
でも授業中は授業を聞いて、勉強をすることを優先しなければならない、という、大人からすれば当然のことでも、子供たちには伝わっていなかったのです。
とにかく、連絡がとれるママ友たちと、自分の子供を説得し、やめさせるという運動を続けました。
そして、学校とも連絡を取り、このような事態を見逃すわけにはいかない、なんとかしたい、という思いを伝えました。
2か月ほどたち、子供たちが理解をし始めた頃、ようやく収束にむかいました。
ギャングエイジの学級崩壊も同じように
三男のクラスでも、同じような状況になったとき、先生への働きかけ、親たちの連携がありました。
ただ、子供たちは大きくなっており、なかなか親の言うことも先生の言うことも聞きたがらない年頃ではありました。
一進一退を繰り返し、結局は学年が変わったときに担任の先生が変わったことで収束にいたった感じです。

ただ、小学6年生になった今でも、学級全体を巻き込むようなことは少なくなりましたが、同じような状況を繰り返してはおさまる、ということがまだ見られます。
やらないことがカッコいい?
つい先日も、我が家の三男の授業態度について先生から注意がありました。
小学校の高学年から中学生にかけては、思春期の入り口でもあり、大人の言うことを聞かないのがカッコいい、という風潮があるのでしょう。
自分のことを振り返ってみても、親に言われること、先生に言われることを素直に聞いていたか、と言われればそうでないときもあったと思います。
でも彼らは、「本当はやってはいけないことはやってはいけない」という本質的なところは理解しているはずなのです。
先日もその話で三男と話し合ったばかりです。
いけないことはわかっているけれど、反抗してみたい。
その小さな反抗が、全体の大きなムーブメントになってしまう。
そして、最終的には学級崩壊に至ってしまうことがあるのだと実感しています。
親ができること
このような事態に直面したときに親ができることは、とにかく自分の子供の言い分を聞くことなのかな、と思っています。
なぜこのようなことになったのか、なぜ悪いことをしているのか。
そして、それをやってもいいことなのか、ダメなのか。
根気よく話をきき、授業中の態度としてふさわしいのはどういったものなのか、という話をしっかり親子でする。
そして、学校側にも働きかけていくことが大事なのかなと思います。
気がついたときが動くときです。
とにかく自分の子供をしっかりと止めること。
授業中に騒ぐことはカッコ悪いということを広げていくこと。
いつか、その状況は改善されると信じて子供を送り出す覚悟も必要ですよね。
先生がたとも密に連絡を取り合うことも大事です。
いつかは収まるときがくると思います。
でもそこまでは親も子供も踏ん張らなければならないことがたくさんあります。
そんな時には、私たち親が子供にしっかり寄り添っていかなくてはいけないですよね。
我が家の体験談ですが、参考にしていただければ幸いです。
子供同士のトラブルについてはこちらの記事も参考にしてみてください。




